
『婦人画報』誌で48回にわたり連載されたコラムと関連して選曲された楽曲を調性順に配置。物語性とともに楽曲の美しい連結も見事なコンセプチュアルな盤。各曲の演奏者も非常に豪華なメンバーが並ぶ。さまざまな場面にふさわしい空気を作り出してくれそうなディスクだ。

名実ともに日本を代表する世界的作曲家、坂本龍一による雑誌『婦人画報』での連載をまとめ、彼が選ぶ演奏の音源も集めた、ファンにはたまらないアルバム。時代や様式を問わず選ぶ彼の眼に狂いがあろうはずは無い。3枚組で収録曲もたっぷり。クラシック音楽入門がこういうセットなら理想的。

くっきりなメリハリが耳に新鮮な坂本龍一ピアノ作品集。第3集はCMなど坂本流リリシズム漂う“実用音楽”だが、岡城は音色鮮やかにきらめかせ、ピアニスティックな音姿に仕立てて耳を引きつける。パリコレのための30分に及ぶ長さの曲でもその流儀を貫いて綻びない。電子音による注釈的自作も興趣深い。

98年に発表された坂本龍一のピアノ・ソロ・アルバムのリマスター盤。ライナーノートを書いている村上春樹がプーランクやサティを想起させると言っているが、その気持ちが理解できる演奏である。CMに使われヒットした99年発表曲の「energy flow」なども収録している。

“教授”のアーカイブ集『Year Book』シリーズ第4弾は、80年代後期の未発表や入手困難なレア音源を5枚組で。“世界のサカモト”の進取や先鋭に満ちた音楽的雑食性とその貪欲ぶりに驚かされる。ビル・ラズウェルらとの六本木インクスティックでの即興セッション・ライヴなどはその最たるもの。

坂本龍一が2017年にリリースしたアルバムの曲を12組のアーティストがリミックスしたアルバム。フェネスやアルヴァ・ノト、アンディ・スコット、空間現代らが参加し、原曲を大胆に再解釈して新たな息吹を吹き込んでいる。アルカ、コーネリアスのトラックがとりわけユニークで秀逸。

ガン闘病後初となるオリジナル作。“架空のタルコフスキー映画のサウンドトラック”というコンセプトのもと、打楽器が激しく打ち鳴らされたり、ダーク・アンビエントが立体的に敷き詰められていたりと楽曲の振れ幅は広く音も立体的。フェネス、デヴィッド・シルヴィアンらも参加。

坂本龍一アーカイヴ“Year Bookシリーズ”の第3弾は、丁度「戦場のメリークリスマス」の制作時期でもある80〜84年の楽曲をセレクト。実験的なライヴを中心に構成されたライヴ・ドキュメンタリーとも呼べる内容。いずれもCD初収録という作品ばかりだが、「戦場のメリークリスマス」のライヴも。★

第87回アカデミー賞で4部門を受賞した『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』のアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督による2016年日本公開作の音楽を坂本龍一らが担当。オーケストラや電子音による現代音楽的な独特の世界観で、緊張感漲る繊細なフレーズに全神経を集中せずにはいられない。

YMOのブームが到来する直前の78年秋に発表されたデビュー作を、オノセイゲンが最新リマスタリングしたSACDハイブリッド仕様の紙ジャケ盤。テクノやフュージョン、現代音楽などが混在した坂本龍一の原点となる作品。細野晴臣や渡辺香津美、高橋悠治、山下達郎ほかが参加。

坂本龍一、YMO以前の70年代の作品をあつめた3枚組アーカイヴ集。まだ“教授”ではなく“アブ”と呼ばれていた時代。楽曲は多岐にわたるが、とにかく初出音源満載、とくに「ナスカの記憶」に圧倒された。貴重な写真や丁寧な解説などブックレットが充実しているのもさすがのcommmons仕事。★

シリーズ第15巻。「モダニズムの進歩史観からポストモダニズムの相対主義への転換」(浅田 彰)に対し「過去300年分くらいの音楽が、この40年くらいに凝縮している」(藤倉 大)との主張を対峙、1945年から現在の欧州大陸における“現代作品”を俯瞰。添付CDは音質面も良く整えられた良作。

山田洋次監督作『母と暮せば』のサントラ。映像がなくとも情景が思い浮かぶかのような東京フィルハーモニー交響楽団の優美なアンサンブルが全編を占める。「回想」はバンドネオンをフィーチャーした小松亮太アンサンブルによるもので、ほどよいスパイスとなっている。

“オリジナル・ネーネーズ”のメンバー3名および島袋恵美子からなる“うないぐみ”と坂本龍一が、『CHASM』収録曲「undercooled」の歌詞付きヴァージョンでコラボレート。辺野古新基地建設に反対する基金への寄付を目的とした作品となっており、UAがヴォイス、Coccoがカヴァー・アートで参加している。

85年に発表した5枚目のソロ・アルバムのリマスター再発盤。舞踏家のモリサ・フェンレイからの依頼で書き下ろされた楽曲群で、コンセプトは“架空の民族音楽”。実験的でありながら、自然に溶け込んでくる感触。タイトルに同調する普遍性がある。当時のライヴから2曲をボーナス収録。

84年発表の作品に未発表曲や別ヴァージョンを加えた2枚組。YMOが“散開”した前後の2年近くにわたって録音作業を行ない、漂流するかのように制作された作品。当然のようにYMO的であり、さらにジャズ的、現代音楽的であったりもする。その混沌とした様子が今となっては心地よく響く。

坂本龍一がピアノ&指揮でオーケストラと共演した“プレイング・ジ・オーケストラ 2014”のライヴ録音からの選曲集。「The Last Emperor」などで聴かせる民族音楽的な響きとオーケストラ・サウンドが溶け合う時、そののスケールと美しさが際立つ。意外なほどになじみやすい響きでいっぱい。

82年にリリースされた坂本龍一&ロビン・スコット名義の12インチCD。もともと共同アルバム制作予定が、途中から坂本のソロ『左うでの夢』へと方向転換、その結果アルバムとは別に本盤が制作された。「Venezia」や「Relache」などに、ロビンが新たに歌メロと歌詞を書き加えた異色盤。

81年10月発表のソロ3作目となる作品。YMOの細野晴臣、高橋幸弘、キング・クリムゾンのエイドリアン・ブリュー、仙波清彦らが参加している。当時は“歌がなければ……”といった印象も一部で持たれていただけに、Disc2に収録されているインスト・ヴァージョンで、往時の印象と音作りの細部を確認できる。

2005年から10年間、多彩なメロディと関わる中で制作してきた音源を、未発表/未収録作品を中心に編年体で綴った2枚組。女声合唱に始まり、実験的なCM曲、ラヴェルの「ボレロ」を意識したというオーケストラ作品など、演奏手法も多岐にわたる中、テン年代に入るに伴い、オーガニックさとノイズがないまぜに。

タイトルごとにテーマを掲げ、音楽を紹介していく人気シリーズの第14巻。“日本の伝統音楽”をテーマに、北海道のアイヌから沖縄まで各地の民謡、雅楽、文楽など、独自の進化を遂げてきた日本における古今東西の音楽を幅広く紹介している。これまでのシリーズと同様、充実の解説もあり。

70年代末“とんでもない輝き”を放って現れ、今も現役で歌う酒井俊が、坂本龍一をはじめ、J-POP、Fusionの強者を集めて歌う名曲の数々を収録。時代を感じさせるアレンジや音響効果も含めて、時代とともに生きる個性の存在感を伝える9曲すべてが光り続ける。

「騒音への欲求」が20世紀“現代社会”に必要とされた楽音であり、西洋音楽が目指した方向性であるとの論。そうした中から生み出されてきた「電子音楽」作品が検証される。豪華ブックレットに語られた作品が収められたオムニバスCDは、文字通り時代を俯瞰する音のカタログとして楽しめる。

2013年のNHK大河ドラマ『八重の桜』のオリジナル・サウンドトラック。CD2枚組に詰め込まれた坂本龍一の美しいメロディによる壮大なテーマ、そして、織りなす幸不幸のなか可憐な少女から気高い女性へと成長する主人公・八重に寄り添うような中島ノブユキの劇中音楽に満たされる想いだ。

日本では16年ぶりとなった2013年5月のオーケストラとの共演からセレクトした一枚。『八重の桜』テーマ曲や、「Merry Christmas Mr.Lawrence」などの傑作群を、ゆったりとしたスケールで披露。ドラマティックなオーケストラの演奏を駆使して、さまざまな映像を次々に呼び起こす技は、“教授”ならでは。

NHK『坂本龍一 音楽で楽しむ大河ドラマ』で放送された歴代の大河ドラマ52作品の中から、坂本龍一が自身で選曲した16曲を収録。武満徹、三善晃、宇崎竜童、渡辺俊幸、岩代太郎といった蒼々たる顔ぶれによる作家陣の、当時としては実験的でかつ先鋭的なサウンドに驚かされる。

毅然とした品の良さ――そんな日本の魅力をはっきりと示してくれる2013年のNHK大河ドラマが『八重の桜』だ。そのテーマを書き上げた坂本龍一が思い描くそんな芯のようなものが、このOSTのすべてのナンバーに共通している。第2集といえども、その質感は少しも衰えない。

NHK Eテレとも連動している坂本龍一監修の音楽全集『音楽の学校(=schola)』の“20世紀の音楽I”だ。シェーンベルク以降を取り上げている。CDは参考資料という意味合いだが、さすがに採り上げた曲や演奏はよく吟味されている。本のほうも坂本らの座談会や論文、曲目解説など充実している。

いわずとしれた2013年NHK大河ドラマのサントラ。明治という日本の夜明けを見事に生き抜いた女性の覚悟と心根を壮大なオーケストレーションに載せた“教授”によるメイン・テーマに加え、力強さのなかにも愛しいまでの優しさを潜ませた中島ノブユキの楽曲が、主人公・八重の生きた時代の風を感じさせる。

NHK番組の連動CDブック第11巻はアフリカの伝統音楽。連想されがちな打楽器の曲だけでなく、言葉によるリズムや動物との会話とも思える歌まで、原始的で素朴であるがゆえ直接魂に訴えかける音楽の数々が聴ける。書籍の解説を読んで驚く曲もあるので、読みながら聴くことをお勧めする。

中山美穂と向井理主演の映画『新しい靴を買わなくちゃ』のサントラ。パリでオールロケを敢行した恋愛作品とあって、劇伴も気品と洒落っ気を行き交うようなメルヘンチックなものに。ともにピアノを主に操るからか、シンプルな鍵盤の作風も多い。サンプリングを多用した「Bar」は坂本らしい着想だ。

ジュディ・カン(vn)、ジャケス・モレレンバウン(vc)とのアコースティック・トリオによるポルトガル録音。「メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス」「美貌の青空」などの定番を、新たな息吹とともに楽しめる。2012年現在の坂本龍一の“境地”が伝わる一枚といえようか。

10巻目となった“教授”完全監修の音楽全集CDシリーズのテーマとは“映画音楽”。欧米の作品を中心に坂本龍一は映画のなかで映像と一緒に流れる厳選24曲を選びだした。楽曲解説、映画音楽史などとともに“教授”を中心とした座談会などを収録したブックレットの価値も素晴らしい。ただ価格は?

2010年秋の北米ツアーと2011年1月の韓国でのピアノ・ソロ・ライヴを収録したもの。MC SNIPERのラップと坂本のピアノとが激しくぶつかりあうセッションから始まり、ベスト的選曲の代表曲を、繊細なタッチと美しい音色のピアノで次々にプレイしていく。とてもネイキッドなアルバムだ。

今回のテーマ“サティからケージへ”は、ポストモダンという言葉を強く意識させる、これまでで最も本シリーズらしい内容。選曲者たちによる対談にも自己言及的な発言があちこちに現れており、楽しくも興味深い。「天国の英雄的な門への前奏曲」は、坂本龍一による録り下ろしの音源。

坂本龍一が沢井一恵の委嘱によって初めて箏協奏曲を創作。冬、春、夏、秋をモチーフとした四つの楽章は、人生の四季と呼応する。グバイドゥーリナの「樹影にて」は、N響との初演(18年)以来の待望の再演。二人の傑出した才能が筝に見出した新たな美の世界をファンタジックに開花させている。

市川海老蔵と瑛太が主演の3D映画『一命』のサウンドトラックを坂本龍一が担当。時代小説をベースにした映画のトーンに合わせ、笙や鼓や笛を使用した、緊迫感あふれる世界が展開される。和楽器とストリングスの同居がドラマティックでスケールの大きな音像に結実している。

3年ぶりとなるコラボ第2作は、「0318」から「0429」まで、日付を曲名に冠した2枚組、全24曲。2011年3月11日の震災(とそれ以降の事象)は、当然影を落としているのだろう。クリスチャン・フェネスらしい静謐な緊張をたたえた曲調の中に、坂本龍一らしい情感の発露が滲む。アルバム表題は“川”の意。

音楽の“特異点”にスポットを当てることで、新たなスタンダードを作っていこうという意志に貫かれた、CD付き書籍の第7作。クラシックの権化とでも言うべきベートーヴェン音楽のサムシングが、グールドとバックハウス、ブーレーズとフルトヴェングラーの異なるスタイルから共有物として浮かび上がる面白さ。その音源を坂本龍一・浅田彰・小沼純一による対談を読みながら味わう愉しさ。シリーズの背景にあるであろう、録音文化が積み上げてきた“音楽アーカイヴ”への敬意と愛情が、これまで以上に明快に感じられる。

ディスク1は坂本龍一が鍵盤楽器を弾いて大貫妙子が歌い、ディスク2はインスト。シンプルな音での“スロー・ライフ”な仕上がりにテーマが表われているように思う。どちらかが作詞/作曲している曲がほとんどで、ディスク1の「3びきのくま」は唱歌、「Antinomy」の歌詞は書き下ろし、「a life」は新曲である。B6版の書籍に近い大きさのパッケージ。

非クラシックもテーマに全30巻で構成する、CD付きの音楽全集。第6巻は“古典派”なのだが、総合監修で、てい談・対談も担当している坂本龍一は、古典派のくくりを問い直すことを主題にしている。そうすることで、古典派の特徴が浮き上がってくるという仕掛けだ。ユニークに思える選曲は、名曲を中心にしながらも個性的な演奏などを含んでいるが、それにも理由があることを解き明かしながら進められていくので、多少難しいかもしれないが、話についていけるだろう。曲目解説など坂本がタッチしていない“付録”が親切丁寧なのが嬉しい。

99年に発表され、長く廃盤状態だった映画『LOVE IS THE DEVIL』のサントラのリイシュー。リミックス・トラックが追加収録されている。ピアノとシンセサイザーだけを使い、音によるペインティングのような感覚的な「Couch,Set Up,Canvas」は、彼のソロ作としても上位に入る出来かも。

スキッと明晰、かつ計算づくのラヴェルの音楽。それと坂本龍一の音楽に、ある種の同一性を感じる人は多いかもしれない。そのラヴェルへの思い入れを坂本が、時に専門的に、時に音楽ファンのごとく語る。対談も選曲も演奏の選択も、ことごとく興味深い。

あらゆる音楽を並列して聴けるようになった現代、普遍性をもったスタンダード(標準)=本当の“古典”は何か。それを作り出そうという野心的なプロジェクト(坂本龍一総合監修)が“スコラ”であり、充実のブックレット+CD(音源はレーベルを横断して収録)全30巻が予定されている。第3巻はドビュッシー。その影響は、武満徹はもちろん、ブライアン・イーノやレディオヘッドにまで及んでいる、とする視点が新鮮だ。CD1枚分のみと音源が数少ないのは残念だが、むしろ選りすぐられたエッセンスとして聴くべきだろう。

坂本が2009年春に行なった国内ツアーのライヴ録音から、27曲を自らセレクトしたアルバム。どんな内容・性格を持つ曲であれ、根底にあるのは透徹した眼差しと鋭い耳、どこか高貴な感性。そしてそこから生まれる知的で澄んだ静けさ。聴き惚れた。★

先鋭的なダンスリー・ルネサンス合奏団が、坂本のオリジナル作品や沖縄や朝鮮の民謡を取り込んで81年にリリースした2枚のLPアルバムからの抜粋。ここではヨーロッパと坂本作品だけで構成。今や実験的なにおいを感じることはなく、両者が響き合った美しい世界だ。

オリジナル・アルバムとしては約5年ぶりとなる作品。ピアノを基本としながらも、シンセや自然音などがミックスされた、アブストラクトなチル・アウト・ミュージック集となっており、静かな覚醒感が漂う。価格の異なる2種類のパッケージが用意されている。

グールドはビートルズと同じように強烈な存在だという“教授”が、なるべくバッハを外して選曲したという。強烈に個性的な演奏もあるが、意外にも素直にロマンティックなものもあって、グールドの新たな魅力が味わえる。坂本お勧めのブラームスは、深く美しい。

87年発表の7作目のソロ。プロデュースは、さまざまなユニットで活躍するビル・ラズウェル。沖縄音楽やバリ島のケチャなどをファンキー・ミュージックに取り込むなど、当時としてはかなり実験的なサウンドである。イギー・ポップやブーツィー・コリンズの参加も話題になった。

坂本龍一総合監修による音楽全集の記念すべき第1弾。強気の価格設定だが、充実したテキスト(116ページ)と音源とが相互補完する形で、バッハの音楽やその音楽史的位置づけなどに関して理解が深められる点が従来のコンピ盤との決定的な違いだ。後続への期待も高まる。

教授の2008年最初のリリースはピアノ・ソロのシングル。民営化されたJPと日本テレビのCMタイアップ。どこかで聴き覚えが。ニューヨークのスタジオでグランド・ピアノ1台にて収録された音は、透明感ある柔らかな音色で、陽だまりのような温もりがある。

映画『トニー滝谷』(監督・市川準、主演・イッセー尾形、宮沢りえ)のサントラ。全編にわたり坂本龍一のピアノによる透明感と孤独感が美しく漂う作品。聴いていて連想させられたのは、キース・ジャレットの「ケルン・コンサート」だが、さらに物悲しさが染入る。★

フランソワ・ジラール監督の映画『SILK』のサウンドトラック。叙情的かつ詩的な映像がさりげなく纏う、シルクのように滑らかで甘美なサウンドに魅せられる。欧州と日本を結ぶシルクロード、そこに滔々と流れる旅情の音楽。優美でアンビエントな旋律に心震える傑作だ。

フェネスに続いて坂本龍一が選んだコラボレーターは、エレクトロニカ・シーンの要人クリストファー・ウィリッツ。明滅する電子音と催眠的なドローン、ニュアンス豊かなグリッチ・ノイズなどが混ざり合い、桃源郷のように美しく眩しい音響空間へと誘ってくれる。

坂本龍一と、彼のソロ・アルバムにも参加していたウィーンを拠点に活動するラップトップ・ミュージックの気鋭クリスチャン・フェネスのデュオ作。基本的にはエレクトロニカということになるが、きわめて有機的で映像的なサウンドは聴き手を静かに興奮させる。

2004年の『CHASM』を豪華なメンツがリミックス。ファン必聴だが、音楽というよりはノイズだった「Coro」を2曲目に入れるあたりが教授の教授たるゆえんなのに、このアルバムではカット。しかしYMOファンには(14)の“Haruomi Hosono remix”なんて興味津々でしょ?

前作『/04』同様、“ゆるみ系ベスト”と呼ばれているこのアルバムは、彼の代表曲をピアノだけで演奏した曲集。全曲、新たに弾き直されたもので新録音。どうにもイライラしてしまった夜に気持ちを落ち着けたい、なんて時に最適かも。

柳楽優弥主演のヒット映画の坂本龍一によるサントラ・アルバム。彼らしいピアノ・ソロによるトラックも多いのだが、実はサントラでこそ実験や冒険をするヒト。この作品では、アジアを舞台とする映像に、あえてケルティックな響きを持つ音楽をぶつけている。

72年に岡本一郎が結成したダンスリー・ルネサンス合奏団が81年にリリースした2枚のアルバムから編纂したコンピ。30種類を超える中世ヨーロッパの古楽器を使い、沖縄や朝鮮の民謡からヨーロッパの音楽まで幅広く収録。不思議な癒し効果のある作品。

回を重ねるごとにシンプル化が進むこのコラボレーションは、3度目にして世界の調和をキーワードに。歌うというより、つぶやくシルヴィアンの声と素朴な演奏が彼のソロ『ブレミッシュ』にも通ずる。SKETCH SHOWも参加し、ひそかな“YMOヴァーチャル再結成”も。

坂本龍一とモレレンバウム夫妻によるボサ・トリビュートの続編。夫ジャキスのチェロがいいだけに、あまりに凡庸な女房のヴォーカルがつくづく惜しい。コンサートで教授が言及していたジョビンとショパンの類似性に迫ってくれたほうが、プロジェクトとしての甲斐があるのでは。

クラブ・ミュージック、映画音楽クリエイターとして活躍する半野喜弘、矢坂健司を中心としたユニット“hoon”が、“ママと赤ちゃんの笑顔のために”制作した胎教/環境音楽集。ドビュッシー、サティなどの楽曲をアンビニエントにカヴァーしている。“監修”として坂本龍一も参加。

80年代前半に作られた、坂本龍一のTV番組のテーマ曲、未発表のインストゥルメンタル作品、同じく未発表のコンピレーション・ワークスを集めたアルバム。11曲目の「Snake & Lotus」と13曲目の「82.7.7 Yano Music No.1」が未発表曲。

坂本龍一が1981〜84年に制作したCM音楽を19曲。CM音楽は、究極の商業音楽であると同時に、制作者にとってはいろいろな意味での実験の場にもなる。クライアントの要求のなかで、新たな坂本ワールドの芽がヒョコッと顔を出している箇所もあって、興味深く聞ける。

ブライアン・デ・パルマと坂本龍一の『スネーク・アイズ』に続くコラボレーション。全体的にきわめて静かな音楽だ。だが静かなのに力強い、荘厳という言葉が当てはまりそうなオーケストレーション。(13)(14)はピアノ曲で「energy flow」を思い出させる名曲。

タイトルどおり、CMおよびTV音楽を集めたベスト盤。当然、短い曲が多く50曲収録となっている。これだけ曲数が多くてもメロディ・メイカーとしての特徴がはっきりと感じられるところはさすが。えっ、この曲って……といった驚きも多い。★

サウンドスケープ……そんな言葉を坂本龍一の映画音楽に感じていたことだが、こうしてクロニクルに振り返ると、もっと根源的なエモーショナルな温度感を感じてやまない。それを分かりやすく解説している本人のライナーがまたこの上なくありがたい。★

初アルバム『千のナイフ』から『AUDIO LIFE』まで、ソロ・ワークにおけるベスト・ソングを収録。アジアから西洋、アフリカ、中南米と、あらゆる要素を取り込みながら自己の音楽を構築するコスモポリタン・坂本の魅力が凝縮されている。

ヨウジヤマモト・コレクションの音楽として坂本龍一が演奏・プロデュースし、96年にリリースされた企画盤の再発。全1曲約35分、坂本のクラシック・ピアノ・ソロのみが延々と展開する。彼の流麗なタッチが存分に堪能でき、とくに終盤の攻撃的なプレイは圧巻。

アフリカ体験を通じて書き下ろした12曲を収録。アフリカの人たちのダンスとからみ合う坂本のピアノ、初めて聴くピアノの音色ヘの子供たちのピュアな驚きと感動、象に聴かせる音楽など、大自然と一体になった喜びに満ちた調べが、豊かな感情を伴い伝わってくる。

教授が手がけた最新サントラが、このNHKスペシャル・シリーズで放映中の「変革の世紀」。キング牧師の“I have a dream”の名演説がバックに微かに聞こえる演出といい、アレンジは絶妙。現代世紀の抱える混沌と調和、希望と挫折の旋律が心の琴線に響く。★

教授による2本の映画のサントラを集めたアルバム。全体を通してジョン・ケージを思わせるようなかなり現代音楽的なアプローチ。特にドキュメンタリー『DERRIDA』は能にも通じる間を感じる。また『アレクセイと泉』は教授ならではの音の世界観を楽しめる5曲。

静かなピアノの単音とシンセとの静かな語らいに入り込み、音の会話に優しく包み込まれる。合間には神経に触るサイレン、ベル、烈風などのノイズが包みを切り裂く。ヴァーチャルというのか、抽象の世界を漂いながら坂本のイメージを体感する。

99年に行なわれた坂本オペラ『LIFE』の大阪城ホール及び武道館ライヴから、教授自身で音楽部分を抽出した2枚組。戦争と革命、生命の進化、科学とテクノロジーなどの歴史を辿りながら、21世紀に向けて地球環境や愛など人類共通の願いをメッセージ。

坂本龍一の参加が注目され電子音楽イン・ジャパン・シリーズの一枚として再発された、木管奏者27歳のデビュー作。オリジナル・ライナーにあるように、坂田明の師匠筋という方の情熱的なプレイが、セッションの牽引力となっている。数々の伝説も残す偉人。

話題にはこと欠かない大島渚最新作のサントラ。噂の松田龍平もいいが、坂上二郎とトミーズ雅もいいぞ。坂本龍一の音楽は冷え冷えとしたピアノの旋律を中心に、クールな現代音楽風。でも、何がいいって、坂本龍一が出演しなかったのが良かったりして。★

坂本龍一が手がけたオペラ、「LIFE」。バラ売りもされている大阪、東京それぞれの公演の模様を収録した2枚のCDに、坂本自身によるスケッチやノートなど膨大な素材をまとめたアートボックスを一つののボックスに収めた豪華版。限定なのでお早めに。

朝日新聞創刊120周年記念の坂本オペラ『LIFE』の東京公演分の2枚組。インスト、歴史的スピーチ、オペラのために集めた著名人のメッセージ、歌とコーラスをコラージュのようにちりばめながら、過去から未来への“人間の営み”を荘厳に奏でている。

地球環境、愛、救い、そして共生をテーマとした創作オペラの音楽。戦争と革命、科学とテクノロジー、生命の進化といった内容が、歴史的な映像、コンピュータ・グラフィック、身体表現、インターネット技術などによって示され、そこに坂本の音楽がとけ込む。

現在の姿からは想像しにくいが、この人の活動拠点は、当初はフュージョン・シーンだった。70年代後半から80年代初頭にかけての録音を集めたこのアルバムでも、セッション・マンとしての器用さがうかがえる。“癒し”を期待して聴くとずっこけます。

このセットを聴き通して思った。教授は進境を続けているのか? ひょっとしたらもうずっと前から彼は同じ場所にいて、異なる意匠で透徹した本質を発しているだけじゃ(無論否定的な意味でなく)? 遠く離れた我々の感性がやっと彼に近づき始めたのか?

大きな話題を呼んだ坂本龍一創作オペラ『LIFE』のシンセ・ヴァージョン2枚組。世界各国の民族楽器や固有の旋律、言語と発声を活かした“音”と“歌”そして“話”が、荘厳な雰囲気のなかで奏でられる。進歩・発達とは何か、を確認するかのように。

さすが世界の“サカモト”と、こっくりさんせずにはいられない超モダン・ミュージック盤。このスペースでは何も語れないが、深くて、精緻で、情緒にとんでて、視野が広くて、刺激的で、示唆にとんでて…と、保証できることは数多い。エラいアルバム。

(1)はTVでお馴染みのCM曲。元気の出る薬っぽくない淡々としたピアノ・ソロが逆に印象的。(2)は夜のニュース番組のテーマ曲で、教授の知的な雰囲気が“いかにも”という感じ。(3)は映画『鉄道員』の主題歌のピアノ・ヴァージョン。品の良さが活きている。

フランシス・ベイコンを題材にした同名映画のサウンドトラック盤で、ピアノとシンセサイザーだけで完成されている。静けさと激しさとが、奇妙なバランスを保ちながら共存する。本人のコメントにもあるように、ソロ作品として聴いても違和感はない。

オーケストラ組曲「untitled 01」をエレクトロニクス・ミュージックの個性派アーティスト11組がリミックス。ブレイクビーツ、ドラムンベース、アンビエント、エレクトロニカ、音響系など、実験的な電子音響のオン・パレードだ。知的刺激も満点。

楽譜やデータFD添付などでも話題を呼んだ教授WP移籍第1弾の通常盤。即興的にモチーフをためていき、数々のスケッチから選んだというピアノ・ソロ・アルバムは、なるほど“ピアニスト”坂本龍一を納得させるものばかり。まだまだ“現役”は伊達じゃない。

教授のピアノ・ソロ作品で、CDとフロッピー・ディスクに入った演奏データと楽譜がセットになっている限定盤だ。教授がその音楽的背景にしていたフランス近代のピアノ音楽を想起させる曲が並んでいる。タイトル通りに根っこを披露している作品である。

本人も忘れたい『子猫物語』を含めると、坂本龍一が手掛けたサントラは10枚目になる。お釈迦様と輪廻転生がテーマだけに、東洋音階を基調にした奥の深いサウンド作り。映画音楽でもひとつの頂点を極めたといっていい。(18)はボーナス・トラック。

本作は、坂本龍一がグート・レーベルを通し発表してきた楽曲たちの中から、特に今の坂本龍一らしさが出ている楽曲ばかりを全部で14曲、73分ぎっしり詰め込んだ作品集。アルバム未収録曲や初CD化曲など、坂本ファンならぜひ手元に欲しい、バラエティに富んだ1枚。

全1曲をピアノだけで弾き通すのだから、ファッション・ショー用に録音されたとはいえ、むしろクラシックの作曲家/ピアニストとしての作品、そう捉えるべきだろう。『戦場のメリークリスマス』に比べ叙情を抑えた表現が、約1時間、途切れることなく続いていく。

ここ数年、映画のサントラなどを中心とした音楽家として活動し続けてきた坂本龍一。本作は、これまで彼自身が作り上げてきた芸術音楽を、1枚に集約したベスト盤。しかもすべてピアノ・チェロ・ヴォイオリンのトリオ編成で新録してる点が、嬉しい限りだ。★

過去に発表された作品の中からセレクトした12曲。坂本龍一の、作曲家としての優れた才能を再確認できるアルバム。映画のために作られた、美しいメロディ・ラインを持つ、おなじみの楽曲も収められている。彼の内に在る“アジア”性も浮き彫りになり、面白い。

81〜87年にアルファ、ミディに録音した3枚のオリジナル盤、2枚のサントラ、M.フュンレイの舞踏曲、ピアノ曲集、メディア・バーン・ツアーのライヴ、シングル・コンピレーション2枚で構成した10枚組で、このジャンルを越えた活動ぶりも坂本ブランドならでは。YMOでの活動とだぶった時期の作品が中心というせいもあって、改めて聴くと彼のヨーロッパのクラシックを太い幹にした音楽的知性といった面が大きく浮かんでくる。全集用解説等はなしだから熱心なファンも飛びつきにくい? 新マスタリング。

岡本一郎をリーダーとする古楽の演奏グループ、ダンスリーと坂本龍一との共演盤のCD化。(4)は坂本のオリジナルだが、それ以外は13世紀から14世紀イタリア、フランスなどのダンス音楽を取り上げている。古楽器の響きと相まってホッとできる音楽だ。

ローリング・ストーンズの67年のサイケなヒット曲の贅沢なカヴァー「ウィ・ラヴ・ユー」のオルタネイト・ミックス・ヴァージョン(1)をフィーチュアした3曲入りCD。(2)はアルバム未収録の新曲。(3)は『戦メリ』テーマ曲のハウス・ミックス・ヴァージョン。

日本人ミュージシャンでもっともワールドワイドな活躍をしている坂本龍一の、ヴァージン・レーベル在籍時の音源を集めたベスト・アルバム。ベストといっても、(1)(2)(3)(8)(9)(12)はオリジナルとは別のヴァージョンを収録しているので、マニアにはうれしい1枚。

今年1月に行なわれたオーケストラ・コンサート「f」のために書かれた協奏曲「untitled 01」をCDエクストラ仕様でアルバム化。嘆きから救済に至る道のりは長く静かだ。第2楽章のジャングル・ミックス(5)でリミックスに挑戦したい方はパソコン買うべし。

坂本龍一が初めて連続テレビドラマの音楽を担当したことで話題の1枚。大ヒットした主題歌(1)の、“Sister M”という謎の女性ヴォーカリストの透き通る声が素晴らしい。インストゥルメンタル曲にも、彼らしい“映画的な”スケールの大きさを感じる。

同時発売のアルバム『1996』に収録されなかった未発表テイク3曲と、CMに使われた(1)で構成された特別編集盤。どうしてこれがアルバムに入らなかったのかと思える美しい曲ばかりで、クラシカルな響きの中に温かみを感じさせる坂本ワールドは健在だ。

アルバム『スムーティー』からの2曲を、東京/NY/LAの3人のリミキサーが手がけた6曲入りミニ・アルバム。坂本のトラックをダシに、リミキサーが自由な表現を行なっている。その個性の違い、狙いの違いを楽しむことのできるディープなマニア向け。

作詞に大貫妙子や高野寛、宮沢和史などを迎えた本作は、ポップで“軽音楽”な作品に仕上げられている。ボサ・ノヴァの香りも漂わせる、淡彩画のようなやわらかで静的なサウンドだ。細野や幸宏の味わいも感じられる「最新型のムード音楽」。

ロック/ニューミュージック・シーンで活躍していたギターの大村憲司が78年に発表したソロ・デビュー作。当時オーディオ・ファン向けに作られていたプロ・ユース・シリーズの1枚で、エリック・クラプトンの(3)では歌も披露。プロデュースは深町純。

1994年10月7日の武道館のコンサートを収録したライヴ盤。人力/機械力が一体となったバンドが、前半に新作、後半に過去の代表曲をプレイしている。やっぱり(8)は名曲。2曲多く収められたビデオもリリースされているので、そちらの方もチェックのほどを。

『スウィート・リヴェンジ』の4曲をグラミー・ウィナーのマーシャル・ジェファーソンと森俊彦がクラブ・ミックスに。ヴァージョン違いを含め4曲のリミックスを収録。「制作者の意図によりノイズが入っている箇所があります」というクレジットが泣かせる。

グート・レーベル第1弾として登場したアルバム。今井美樹、高野寛、ロディー・フレイム、ホリー・ジョンソン他、豪華なゲストがヴォーカリストとして参加。ファンには喝采モノの美しい歌詞カードと、マジックボックスのようなCDケースがお洒落。

本人も忘れたい『子猫物語』を含めると、坂本龍一が手掛けたサントラは10枚目になる。お釈迦様と輪廻転生がテーマだけに、東洋音階を基調にした奥の深いサウンド作り。映画音楽でもひとつの頂点を極めたといっていい。(18)はボーナス・トラック。

80年の『B−2ユニット』から91年の『ハートビート』まで、レーベルを越えたコンピレーションの第2弾。珍しい鈴木慶一作詞の(1)、A.リンゼイとの(2)、I.ポップとの(4)、T.ドルビーとの(9)などの共演物が光る。(11)ほかの映画用の作品の多彩さも楽しめる。

オリバー・ストーンが制作総指揮を務めた近未来のロスのTV局を舞台にした連続TVドラマのサントラ盤。音楽は坂本龍一の書き下ろしで、冷たい美しさを持つミニマル仕掛けのもの、ゾンビーズの(14)以降の5曲は挿入曲として使われたオールディーズ。

ヴァージンに残した“世界のサカモト”時代の録音を時系列に配列。さらにミックス違いの(1)、(11)、(12)の計3曲の日本未発表トラックを含むベスト・アルバム。コラージュ手法を極めた完成度という記名性と、作品自体の匿名性、普遍性の対照がおもしろい。

坂本龍一が手がけた映画音楽のベスト・セレクション。たとえようもなく壮大で優雅な雰囲気に浸れて、午後の紅茶タイムのBGMにも最適です。個人的には、中年夫婦の愛のかたちを描いた「シェルタリング・スカイ」のひたひたと胸に迫るようなテーマが好き。

日本の先鋭的なフュージョン・ムーヴメントを記録したベター・デイズ・レーベルの香津美のベスト盤。この坂本龍一(key)、マイケル・ブレッカー(ts)、マイク・マイニエリ(vib)etc.という参加メンバーがすごい。ベターというよりサプライズ・デイズだよ。

70年代後半にロック〜フュージョンのミュージシャンの交流から生まれた作品を多く残したベターデイズ・レーベルの作品を坂本龍一を軸に編集した企画物。初ソロ『千のナイフ』、渡辺香津美を中心とするスーパーバンドKYLYNなど他流試合の楽しみに溢れた演奏集。

ヴェネズエラの新鋭ピアニストによる坂本龍一作品集。オトマロという少しトボケたような響きを持つ名前とは裏腹に、リズミカルかつ情熱的なタッチで聴かせる所がやはりラテン系ならでは。特に(5)(7)等は、坂本自身の高尚なピアノ演奏版より楽しめる面も。

ジュリエット・ビノシェ主演の映画『嵐ヶ丘』のサントラ盤。作曲者・坂本龍一の指揮によるロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラの演奏で、怖いほど劇的な世界が大胆/繊細に描かれている。教授自身のソロ・ピアノによるテーマ(25)は日本盤のみ収録。

スペインの映画監督、ペドロ・アルモドヴァルの最新作のサントラ盤。坂本の音楽は、小編成のストリング・アンサンブル、ピアノ・ソロなどの小品を中心に、彼の個性を押し出すのではなく、古典的な映画音楽のイメージに沿って甘く、叙情的に展開。

9年ぶりの共演ミニ・アルバム。シルヴィアンのヴォーカルを含めて、再会セッションというよりは、再演セッションというイメージが濃いサウンドが、ミーハー人気がピークにあった10年前にタイム・スリップさせてくれる。シルヴィアンの熱烈なファン向け企画。

昨年10月に発表された最新作『ハートビート』のタイトル曲3ヴァージョン(1)〜(3)と同盤収録の(4)を収録したCD。クラブ・ミックス(1)とアンビエント・ミックス(2)はこの曲の共作者サトシ・トミイエのMixによるものだが、今の僕の気分には(2)の方が合うかな。

教授のオリジナルにプリンスなどを手かけたプログラマーがダンスミックスすると聞いてワクワクした。しかしテクノハウスをもっと地味変奴(ジミヘンド)ミックスにした感じで反応しなかった。映像やクラブの鮮やかな証明があればまた別かもしれないが…。

坂本龍一、上野耕路、窪田春男といった才人を動員してコラボレーションしたアニメ・サントラ。しかし、本作の目玉は初CD化の[1][2][3]でアニメっ子捕獲作戦を実施。ファンには、ドラマのセリフってのが自己陶酔するのに重要だんだよね。

どんな人とセッションしようとも、絶対それとわかってしまう坂本フレーズが、『ビューティ』以来2年ぶりになるこのソロ作ではとても少ない。個人的にはそれが最大の不満で、有名陣多数参加もインパクトはなく、ハウスの匿名性威力に八つ当たりする次第。

さすが世界の“サカモト”と、こっくりさんせずにはいられない超モダン・ミュージック盤。このスペースでは何も語れないが、深くて、精緻で、情緒にとんでて、視野が広くて、刺激的で、示唆にとんでて…と、保証できることは数多い。エラいアルバム。

「ユー・ドゥ・ミー」は90年代風チャンプルーとでもいおうか……ちょっと強引な表現かな?「ウィ・ラヴ・ユー」はミック&キースの作品のリミックス。ブライアン・ジョーンズに聴かせてやりたい気もするけど。完全に、海の向こうからニッポン及びその音楽を見つめちゃってるみたいですな。

1988年4月のオーケストラ・コンサートで収録された26曲に、同年6月のNYでのライヴ録音3曲をプラスした3枚組ライヴ盤。『ラスト・エンペラー』と『戦場のメリー・クリスマス』の曲を中心に、テクノ時代の名曲なども楽しめる贅沢な構成。

12インチや7インチでしか聴けなかった音源のCD化。(1)と(2)は、トーマス・ドルビーとのコラボレーションによるもの。(4)と(5)は、タイ語によるラップが話題になったナンバー。どちらもミックスの違いを楽しみたい。やっぱりサカモトはCDで聴きたいよね。

12インチのみだった『オネアミスの翼』用の習作バリエーション4曲。世界をひとつの丼とすれば主食はやっぱり御飯なのかと疑問の余地のある人は聴いてみるべき。ときどき伊福部昭になるとこうは正統派SF邦画をめざしたがゆえか。スケールは大きい。

78〜88年までの10年間の数ある名品の中からたったの13曲を集めたベストだが、こうやって思い切って凝縮するとこの人の異能ぶりがよけいに印象的だ。グローバルであたりまえ。メロディ・メーカーとしての魅力もお忘れなく。

『エスペラント』に続く本作は、マリネッティの未来派にインスパイアされて、未来派野郎。これからは、混合文化の中からしか新しいものは生まれ得ないとよく言われるが、そういった意味では、よく溶けあっている。で、このあとは“ダダ”なのかな?

当時世界中で最も注目されていたモリサ・フェンレイのダンス・パフォーマンス、『エスペラント』のために作曲された音楽を収録したアルバム。坂本龍一の創り出すサウンドからは民族やクラシックなどさまざまな音楽を融合したような深いものを感じる。

MIDIレコードを設立して、第1作目の坂本のソロ・アルバム。YMOを散開して初のアルバムだけに、本人のコメントでも「YMOを引きずっている部分がある」と言っていたが、その分だけわかりやすく(?)なっている。またYMOへの決別にもなっている。

78年10月発表の坂本龍一のソロ・アルバム。ちょうどYMOが始まった頃で、ゲスト・ミュージシャンがすごい。YMOの他のメンバー、ギタリストの渡辺香津美、ピアニストの高橋悠治らが参加したサウンド遊戯アルバム。

'80年〜'82年の坂本龍一の作品をセレクションしたアルバム。坂本のサウンドは、ポップ/ロック的感覚から生まれると言うより、やはりクラシック的なオーケストレイションといった匂いがする。シンセサイザーなどの楽器の音色になれてくればくるほど。

「ポップ・ミュージック」のヒットで知られるMのロビン・スコットとの共作。“テクノ・ポップ”という言葉からそう大きくはずれない、機知に富んだエレクトロ・ポップが並んでおり、懐かしくも新鮮だ。(5)と(7)はアルバム未収録曲。

超大作『オネアミスの翼』のサントラは、サウンド・プロデュースを坂本龍一が担当。コンポーザー、アレンジャーには、元ゲルニカの上野耕路、おしゃれテレビの野見祐二、パール兄弟の窪田晴男が参加して『未来派野郎・SF編』といったするどい仕上りだ。

ベルトリッチ監督のアカデミー音楽賞受賞作。音楽を担当しているのは、坂本龍一、デヴィッド・バーン、スー・ソンの3人。ひと言で表現すれば、坂本はドラマティック、バーンはユーモラス、ソンはシリアス、といったところか。音楽だけでも十分に楽しめる。

大島渚監督、デビッド・ボウイ、ビートたけし共演の『戦場のメリー・クリスマス』はカンヌ映画祭にも出品され惜しくもグランプリはのがしたものの大変な評判を呼んだ。殊にボウイと坂本龍一のラストのキス・シーンは話題になったものだ。1枚はオリジナル・サントラ、そしてもう1枚は全曲ピアノ・ヴァージョンとして新たに録音し新曲「JAPAN」「CODA」を追加収録。メイン・テーマ「メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス」は日本の伝統音楽と東南アジアの民族音楽を融合した感がする。

'79年の渡辺香津美の『KYLYN』を中心に、渡辺と坂本龍一が日本コロムビアに残したテイクを集めたベストCD。ジャズとロックのジャンルを超えて、気鋭のミュージシャンが集まり、エネルギーあふれる音楽をつくりあげている。
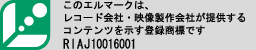
 弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。
弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。